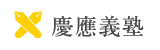橋本陽介君(2001年3月卒/お茶の水女子大学助教)
今回は、2001年3月卒業の橋本陽介君に、在学中に授業を担当した中地譲治教諭との対話形式でインタビューを行いました。橋本君は卒業後、慶應義塾大学文学部に進学し、中国文学を専攻。2011年度から2017年度まで国語科の非常勤講師として本校の教育にも携わりました(この間に大学院博士課程を修了して学位も取得)。2018年4月にお茶の水女子大学助教に就任。文学研究者として研究書から一般向けの新書まですでに10冊の著書があります。20年前を振り返りつつ、現在まで続く本校の魅力や学問に向き合う姿勢について、縦横無尽に語ってもらいました。
入学まで
中地 まずは、志木高と橋本陽介さんとの縁について、本校を志して受験で入ってきた動機みたいなものがあったら伺いたいです。
 橋本 一番は、大学受験したくないのが大きかったです。私の両親は大学を出ていないので、大学受験はすごい怖いものだと思っていたんですよね。朝から晩まで勉強しなきゃいけないみたいな。そういうイメージが一つあったのと、中学の時、『三国志』とか歴史とかがものすごく好きだったので、好きなことやりたいということで、受験しないで大学に行ける早稲田と慶應の高校を受けようと決めました。
橋本 一番は、大学受験したくないのが大きかったです。私の両親は大学を出ていないので、大学受験はすごい怖いものだと思っていたんですよね。朝から晩まで勉強しなきゃいけないみたいな。そういうイメージが一つあったのと、中学の時、『三国志』とか歴史とかがものすごく好きだったので、好きなことやりたいということで、受験しないで大学に行ける早稲田と慶應の高校を受けようと決めました。
中地 それなりに高校受験の勉強はしたのですね。
橋本 そうですね。結構大変だったんですけどね。埼玉の本庄市に住んでいたんですが、当時はあんまり私立受験の塾ってなかったんですよ。だから通信教育をやっていて、今から考えると本当に非効率的な勉強をしていました。もうちょっとやり方いろいろあったなって思います。
中地 県立志向は強かったでしょう。ご両親も反対しましたか?
橋本 いや、受かったらいいよみたいな。受かると思っていなかったみたいですけど。
中地 志木高の試験問題は独特なものでしたか?
橋本 (過去問は)もうめちゃくちゃ難しかったですね。特に国語は全然分からなくて、絶望したものです。圧倒的に長いですよね、当時の作文は。400字だったと思うんですけど、そんなの出てきたらどうしようって思っていました。
中地 何か印象に残っている問題はありますか?
橋本 最初の作文を覚えていますね。渡り鳥に何か発信器を付けて飛ばしたっていう話と、それについて何か書けっていう問題。それは非常に印象に残っています。ただ、解いた時、読解問題が例年に比べて、すごく簡単だと思ったんですよ。1時間目が国語だったんで、いつもちんぷんかんぷんの国語ができたから、これいけるんじゃないかって、そういうポジティブな気持ちになったぐらいです。
中地 元々、橋本さんは国語に志向性があった。文章を読んだり、書いたりが、すごく好きですよね。そういう潜在的な素質も志木高に入学してから開花していくことになるんでしょうね。
志木高の衝撃
中地 入学してみて、何か印象に残っていることや、驚いたことはありますか?
橋本 1年の1学期、とにかく成績を気にしなくなりましたよね。
中地 それはいいことですね。
橋本 要するにそれまでやっぱり点数というか、いかに人より点を取るかっていうことを気にしていました。でもこの学校に入ってからは、人より点を取ったらえらいみたいな、そういう価値観がほとんどなくなって、それよりはやりたいことやったほうがいいとなりました。
とにかくマイナらなければいいみたいなのは(註1)、1年の1学期に結構植え付けられましたよね。国語は本井英先生でしたけど、最初の期末テストをやったあとに、採点に文句を言うなと言われたんです。1点や2点が上がったところで成績は変わらないと。合計点数が間違っている場合だけ持って来いって。今の生徒もそうですけど、4月だけまだ受験してきたときの気持ちが残っていて、5月になると「志木高生」になりましたね。
註1:成績が進級の基準に達しないことを、志木高生は「マイナる」と表現する。
中地 いや、本当に最初シーンとしていた教室が、だんだんくだけてきてね。もうタメ口みたいになった時、君たちも教えがいのある生徒になってくれたなと。
橋本 あと、教科書は使わない、なんでもあり、隣の教室とやっていることが全然違うっていうのが衝撃的で。先生によってやっていることが違うし、下手したらテストもない。どっちかっていうと、文系の先生のほうが自由に授業をしていましたね。面白い授業がいっぱいありましたけど、社会科も教科書を使わなくて、日本史は10月になってもまだ弥生時代で、いつキリストは生まれるのかみたいな感じでした。近・現代史でも、近代っていつから始まるんだよっていう話から始まって(註2)、資本主義からだよ、資本主義っていつから始まるのかっていうと、大航海時代。だから大航海時代やるよって言って、1年間、大航海時代が続くっていう授業、面白かったですよね。
註2:近・現代史は2013年度まで開講されていた社会科の学校設定科目。カリキュラムの改訂で現在はない。
 中地 私は、自由選択の和文講読で、ちょうど『伊勢物語』をやっていた年でしたよね、確か。
中地 私は、自由選択の和文講読で、ちょうど『伊勢物語』をやっていた年でしたよね、確か。
橋本 『伊勢物語』ですね。10人ちょっとの授業でしたよね。
中地 例年、成立するかしないか分からないような自由選択の授業でしたけど、たまたま10人も取ってくれたので、授業が成立したっていう珍しい年でした(註3)。それを取ってくれていた生徒たちは結構、研究者になっていたりしますよね。だから、そういう役に立たないものをあえて取るっていう、学生としてはかなり勇気のいることを橋本さんもやっていたわけですよね。勇気いりましたか?
註3:3年生の自由選択科目は、履修希望者が極端に少ないとその年度は開講されない。
橋本 いや、私は役に立つかどうかなんてどうでもよくなっていましたね。
中地 役に立たないことを学ぶことに、まったく恐れはなかったですか?
橋本 そうですね。文系の授業に関しては、じゃあ逆に役に立つ授業はどれなのかっていう問題が発生してしまうので。あんまりそういう発想はなかったですよね。これが役に立つとか、役に立たないとかっていうような基準でものを見ていなかったと思いますね。
中地 そうですよね。だけど今の生徒は、先生どういう試験が出るんですかって、そこから質問してくるんですよ。それでその試験に合わせたような勉強をどうしたらいいかっていうのを考えるみたい。
橋本 あんまり志木高生っぽくないですよね。試験に合わせて点取ってもね。医学部行きたいなら別ですけどね。
中地 無我夢中になって授業聞いて楽しくて、試験直前になって、先生、試験はどういう試験ですかって聞くんなら、こっちだって、じゃあ一緒に考えようかってことになるわけ。
橋本 試験は教員側も前の日まで何を出すか考えていないこともありますからね。何を出すのかっていわれてもね。
中地 どういう試験をやろうと思って、普段教えているわけじゃないですからね。
橋本 試験のために授業をやるわけ、勉強をするわけでもないですもんね。
中地 そういうところは志木高に入学してくる生徒にはよく分かっていてほしいなって思いますね。だから役に立つとか、立たないとか、試験のために勉強があるとか。橋本さんの場合は、ほぼ1か月でそういう狭い見方から脱出できたんですよね。
橋本 そうですね。大学入試があったら試験で点を取ったほうが良い大学に行けるとか、そういう縛りがあるわけですけど、本校で良い成績を取っても、そんなに良いことない。悪い成績なのは問題ありますけど。ある程度基準を満たしていれば、そんなにものすごいメリットがあるっていうわけでもないですよね。
中地 ただ、外部の人、特に中学生から見ると、留年に対して、すごい恐ろしさを感じていると思うんですけど、実際に留年した友達はなんて言っていますか?
橋本 私の代はあんまり留年がいませんでしたが、一人いましたね。彼はもう全然勉強する気にならないって言っていたんですけど、大学に入ったら逆に勉強が大事であることに気がついたとか言っていましたけどね。
中地 そうなんですよね。私の教え子の中にも、留年したけど大学ですごい頑張って勉強して、大学に残ったのが結構います。だから世間から見ると先行きのない中で発見した自分っていうのが最後のよりどころとなって、その人の人生を決めていくみたいなところがやっぱりあるんだろうなと思います。
課外活動、語学習得、中国体験
中地 橋本さんの場合は新聞部とか自然観察部とか、あるいは夏休みには自分で思い立って中国行っちゃったんでしょう? そういう学業以外のことでの思い出について教えて下さい。
橋本 新聞部は、同期で3年の最後まで残ったのはもうあと一人で、合計二人しかいませんでした。当時は部活っていうのもほぼ放置だったんですよ。今は先生方が運動部をきちっと見ているし、文化部ももちろんそうですけど、当時は運動部ですらそんなにちゃんと見ているかな?という感じでした。
引率についてくるかも怪しいような状況だったので、教員なしでどこか行くみたいなことは普通にあったし、先生は何かある時にハンコをくれるだけっていう感じでしたね。だから無法地帯みたいな感じですよね。勝手に何かをやるっていう。
中地 でもそういう生徒同士の思いつきっていうものがまずあって、それが実現できるような環境が逆にあったっていうことだから。何か思って考えたことが押しつぶされたとか、そういう苦々しい経験っていうのは、まずはないわけでしょう?
橋本 まずないですね。そこが一番いいですよね。これは駄目だっていうようなのは一切。本当は駄目なんじゃないかっていう気がしないでもないこともいろいろありましたけど。あんまりそういう管理がなかったので。
中地 だから失敗したって、大人から責任を押し付けられるという感じは残らないわけですよね。その辺はだから子どもの、生徒の成長が、かなり自由な方向性に伸びていけるっていうことでもありますよね。
橋本 そうですね、そういう価値観が養成されていくというか。勝手にやれよっていうような。
中地 新聞部では、やっぱりそういうのが言論に結びついてくると思うんですけど、どういう言論活動というか、記事を書いていたか、記憶に残っていますか?
橋本 もう、あんまり具体的には覚えていないですね、新聞部時代のことは。ただ3年生の夏休みに中国に40日間行くっていう機会があったんですけど、その時のことを書いたのはよく覚えています。
中地 では、その中国体験というのを、具体的に教えて下さい。
橋本 元々、『三国志』とかが好きで、中国語を勉強したいっていうのがあって、この学校で1年から取っていたんですけど、2年の時、中国語ができるようになりたいってことで本格的に中国語を勉強しはじめました。
中地 語学課外講座ですか。
橋本 はい、そうですね。当時いた先生の旦那さんが北京の大学の先生になるというので、その学生寮に40日間入れてもらったんです。ただ、別に何かがあったわけではなく、ただ40日間放置されたんですよ、北京に。当時の北京は不親切だったし、いろいろひどい目に遭いました。言葉をしゃべらないとどうにもならない状態だったので、すごい修行になりましたよね。
中地 ただ、橋本さんが今、活躍している色々な分野においては、語学の、特に多言語修得のノウハウに、それが元になって広がっていったということもありますか?
橋本 もう、それが一番最初の体験というか、言葉を使うってこういうふうにやるんだなっていうひらめきがあって。もちろん3年生の選択授業で、フランス語とドイツ語を取っていましたから語学に興味はあったんですけど、特にしゃべれるようにするっていう面においては、この時の体験がやっぱり一番大きいですね。
中地 本校では1年生から、いろいろな語学の授業が受けられたわけですが、結局、受講したのは何語と何語ってこと?
橋本 中国語の次はモンゴル語ですね。水野正規先生のモンゴル語。「モンゴル語の授業」だったかどうかは怪しいけど、とにかく。
中地 科目名としては「モンゴル語」。
橋本 科目名としては「モンゴル語」。そのあと3年生の時にフランス語とドイツ語を選択して。
中地 では高3の時は、必修と自由選択の授業で、英語、フランス語、ドイツ語、3か国語をやって、中国語もずっと引き続いてやっていた。
橋本 英語はほとんどやっていなかったですけどね。主に中国語をやっていました。
中地 そういう何か多言語的なものに自分自身で突き動かされてきた、その原点はなんですか? 高3の中国の40日体験?
橋本 そうですね。
文学部に進学するまで
中地 だから学部もすんなり、迷わずに。文学部しかないですよね。
橋本 志木高に入る前からそういうつもりだったので。
中地 当時、悩んでいる人もいたでしょうけど、周りの友達はどんなふうに見えていましたか?
橋本 最初の希望段階で文学部に志望を出した人は40人近くいたんですよね、僕の学年は。だから土壌として文学部的なものが好きな者っていうのは、今もそうですけど、結構いたんです。でもやっぱり現実的な選択として、皆いなくなって。結局10人いくか、いかないかぐらいで第1希望を出した人が収まったんですけど。
中地 文学って言っても範囲が広いから。特に慶應の場合は、ごちゃまぜですからね。そういう状況の中で、大学にバトンタッチということになるのかな。志木高生活について、言い残したことはありますか? 橋本さんが進むことになる、中国文学専攻出身の小林和良先生のことですかね。
 橋本 もうやっぱりダントツで面白かったですよね、小林先生の漢文は。私だけじゃなくて、全校的にも衝撃的に人気がありましたね。
橋本 もうやっぱりダントツで面白かったですよね、小林先生の漢文は。私だけじゃなくて、全校的にも衝撃的に人気がありましたね。
中地 高2の時に、必修で全クラスが小林先生の漢文。
橋本 そうですね、週2時間です。何が面白かったんだろうって考えると、説明が面白かったですよね。くすりともしない真面目な顔で変なこと言っているんですよね、小林先生。どこまで本気なんだろうなっていうのもあって。授業の仕方がうまくて、常に印象に残っていますね。漢文で「仁とは何か」というような話が『論語』で出てきて、仁っていうのは実際よく分からないんですけど、生徒に問い詰めていくんですよね、いろいろ。「君は銀行強盗をやってもいいって言われたら、しますね」とか。そういう問いかけをしてきて。「いや、しないです」って生徒が答えると、「なんでですか、してもいいんですよ」って言うんですよね。「いや、ほかの人が困る」って言うと、「ほかの人が困らなかったらやりますね」って、そういうような問いがあったっていうのは非常によく覚えていますね。でもその指された生徒は、最後まで「やらない」って言ったんですよね。そうしたら小林先生が、「仁者ですね」って言って、不気味ににこりとしていました。
中地 それが仁なんだ、仁と。
橋本 あれはどういう意図でやっていたのかよく覚えていない、よく分からないですけど。
中地 そうですよね、小林先生は。そういう授業でしたよね。でも1年間、それが続いたわけでしょう。
橋本 1年間続きました。テキストは、先生のコピーしたものだったと思うので、ちゃんとした教科書みたいなのは使っていなかったですね。前半はわりと基本。『十八史略』をやったあとに『論語』があって、『老子』をやったのはよく覚えています。
中地 やっぱり面白いね。
橋本 面白いですよね、やっぱり。老子の無為自然っていうのが、その学年の流行語みたいになっていて。「無為にしてなさざるなし」と。
中地 そうですね、はやっていましたね。高校2年で漢文を2時間みっちりやるっていうのはやっぱりカリキュラム的には結構特殊ですよね。
橋本 特に今は無理ですよね。
中地 今は漢文っていうものさえ科目名の中に現れない状況があってね。古文もないし。だから自由選択で、国語の科目の名前を決めましょうっていう時に、当時は国語Ⅱだったかな、確か。そういう極めて単純化されちゃうような名称を、自由選択ではなくしましょう、和文講読、漢文講読。ちゃんとした名前で授業を開講しましょう、というふうに決めた経緯がありました。そう決めたあと、では実際に生徒が取ってくれたかっていうと、そうなった途端に取らなくなっていく。
橋本 小林先生の漢文はすごい人数だった気がしますね。2クラスはあったかな。
中地 小林先生の漢文だけは、だから、そういう状況の中でも残りました。あと、国語表現っていうのがあって、それも多かったですかね。
橋本 国語表現もよく覚えています。本井先生の国語表現ですね。これはすごかったですね。先生が来て、雑誌を作れって言うんですよ。こういう雑誌を作れと。締め切りは何月何日だと。じゃあって言って帰っちゃうんですよ。 それで毎回出席を取るだけで、とにかく雑誌を作らせると。出てきたものに関して、先生がその文章のこれはこうだって採点をおこなうっていう授業で。選択者は多かったので、たぶん4グループぐらいはあったんじゃないかな、4授業ぐらい。4つぐらい雑誌があって、それぞれ勝手に編集長を決めて、勝手にその生徒たちの中だけでなんとか締め切りに間に合わせるんだけど、原稿を出さないやつがいたりして、編集長がガチギレをしたり。隣の班はワンマン編集長が暴君として権力を振るっていたり。ワンマン編集長が停学になった、あの雑誌はもう終わったなみたいなこともあった。だけど先生は一切何も言わない。教員の立場からだとかなり怖いことやっていましたよね。出てこなかったらどうするんだろうって思っちゃう。
中地 妙な信頼関係があったんだよね。先生と生徒の間にね。管理をしないことと管理をされないこととが抜き差しならない緊張関係を生徒と先生との間に生みだすという信頼関係、とでも説明すればいいかな。
橋本 ある程度管理しないとちょっと怖いですよね。
小澤(国語科) 橋本先生が教わっていた国語科の先生方は、中地先生を除いてもうほとんどいらっしゃらないですよね。当時を思い出してみて、「志木高にはこうした面白さがあるんだ、あったんだ」と伝えたいことがあれば教えてください。
橋本 もう20年以上たっているんですけど、ものすごい自由な雰囲気、何やってもいいよっていうような雰囲気というのは、まだ今もずっと続いていて、生徒が自主的にやる、管理されずに勝手にやる。そんな中で、今もこの志木高の生活はものすごく楽しいって言う生徒が非常に多いんですよね。なのでそこはやっぱりすごい大事にしてほしいですね。何かを忖度してやるとか、点をもらえるからやるとか、そういうことではなくて、何かやりたいことを見つける、考えられる時間になるんじゃないかな。志木高にいる時は逆に気付かないかもしれないですけどね。大学に行って、そういう雰囲気が分かるっていうのはあると思います。
志木高非常勤講師として
中地 母校に戻ってきて、教壇に立つっていうのは橋本さんにとってどういう経験でしたか?
橋本 立場が変わるというところがあるにはあったんですけど、自分が出身の生徒として、ここの授業が一番面白かったので、後輩にもやっぱり同じように思ってほしいと思っているんですよね。だからここの授業が一番面白かったなって思ってもらえるようにと思って、ずっと授業をやっていました。
やっぱり小林先生であるとか、本井先生であるとか、中地先生の授業であるとか、そういった授業というのがモデルとしてあります。と言っても、どの先生もかなりキャラが立っていたので、全然真似はできないですけど。自分なりにそのオリジナルは開発すればいいかなっていうのはありました。
小澤 7年間にわたって講師を続けて、最初の頃と最後で、自分の中で変わった点などはありましたか?
 橋本 40人相手というのは、勝手に面白いことをやればいいとは言っても、最初は難しいところがありました。年を重ねるごとに、いい雰囲気は作りやすくなりましたね、自然と。たぶんやっている内容は一緒なんだけど、こちら側の余裕というか、そういうものが見えるからだろうと思います。やっぱり高校の授業は、やっていてすごく面白い。志木高生のいいところでもあるんですけど、レスポンスが早いんですよね。寝ていたからといってそこまで酷い目には遭わないと分かっているから、つまらなければ聞かない。だからその反応を見て、これだと駄目なんだな、こうするとすごく反応がいいんだなっていうようなのがものすごくよく伝わってくる。それが教師としてのスキルアップにものすごくつながるところではあったと思います。
橋本 40人相手というのは、勝手に面白いことをやればいいとは言っても、最初は難しいところがありました。年を重ねるごとに、いい雰囲気は作りやすくなりましたね、自然と。たぶんやっている内容は一緒なんだけど、こちら側の余裕というか、そういうものが見えるからだろうと思います。やっぱり高校の授業は、やっていてすごく面白い。志木高生のいいところでもあるんですけど、レスポンスが早いんですよね。寝ていたからといってそこまで酷い目には遭わないと分かっているから、つまらなければ聞かない。だからその反応を見て、これだと駄目なんだな、こうするとすごく反応がいいんだなっていうようなのがものすごくよく伝わってくる。それが教師としてのスキルアップにものすごくつながるところではあったと思います。
中地 先生っていうものに対して盲目的に服従させるような、先生―生徒関係を強要するような学校っていうのがやっぱりあって。志木はそういう学校の対極にある学校だからね。逆に教員の方が授業内容とか、授業方法だとか、知らず知らずのうちにスキルアップしているっていうところはありますよね。
橋本 一元的に管理して服従させれば、一応、教室空間としてはまとまりあるものにはなるんだけど、私も卒業生として、一切の管理はしたくないので。ただ、一切ノー管理でやった場合にめちゃくちゃにしないようにするっていうのは、かなりスキルがないとできない。最初はやっぱりできなかったんですよね。2年ぐらいやっていくうちに、全然管理しなくても、まとまるようになりました。
中地 それはやっぱり今の教育のテーマで、例えばインクルーシブな環境のある学校、そういうものを目指す動きが一方ではあるじゃないですか。志木高は元々インクルーシブなんだよね。
橋本 そうですね。元々そうなんですよね。
中地 何もインクルーシブになろうと思ってなったわけじゃないんだけど。それができたのは、無理をして自由になろうとした学校ではなくて、先人が不自由を自然に、だけど断固として拒否してくれた学校だからなんでしょう。
学生生活から現在の職場まで
小澤 大学入学後、自分が面白いと思いながらやってきた学問について聞かせてください。
橋本 大学に関しては、正直あんまり面白くなかったんですよね。志木高とは結構価値観が違うので。外から入ってくる人たちの価値観もかなり違うんですよね。受験を経て来るので。それこそ、どうやったら点が取れるかみたいな発想がやっぱり残っているし、何をやったら評価されるかみたいな人も多いし。いまいち面白くなかったですね。高校と違うのは、人数が多いっていうところもあります。いつも同じメンバーで狭い空間でやっているのと違うので。結局、私は志木高で勝手にやるっていうのが身に付いていたので、大学に期待するのをやめて、自分で勉強するっていう方針に切り替えたのが良かったかな。
自分で本をたくさん読んで、面白いことを見つけに行くっていう作業をしていました。慶應は本当にものすごく資料をいっぱい持っている。もうありえないぐらいの資料を持っているし、誰も借りていない。だから、そこでいくらでも面白いものは見つけられるんですよ。研究者としてやっていくのには、その方が良かったんじゃないかなと思うんですよね。与えられたものをやっていたわけじゃないので。
小澤 橋本さんは中国文学専攻出身ですが、「物語論(ナラトロジー)」であったりとか、もしくはノーベル文学賞作家全般であったりとか、とても関心が広く、学問のフィールドを自分で築いています。広がるきっかけは何でしたか?
橋本 これもやっぱり、この分野ならこれ、というようなことをやっていないので、自分の面白いと思うものを手当たり次第やっていくうちに、いろんなものに広がっていっちゃったんです。元々は、中国にものすごく興味があって、現代中国をやり始めて。高校3年の時に、高行健という作家が中国語で書いて、初めてノーベル賞を取った。これが漢文の授業で話題になったんです。それで原文で頑張って読んで。その高行健、フランス文学者だったので、自分もフランス語を勉強したら、そこに何か面白いものが転がっていて。「物語論」に関しては、最初は北京大学に留学中に、向こうの授業で知ったんですけど、日本で勉強し始めたら、分かりやすい本が全然なくて。手探りでいろいろ勉強した記憶があります。
小澤 ガルシア・マルケスをはじめとするラテンアメリカ文学がものすごく好きなことが、橋本さんが書かれた本からも伝わってきます。出会いとか、それからの広がりに、どんなことがありますか。
橋本 これも最初は、中国の莫言っていう作家を読んだのがきっかけです。北京大学にいた時なんですけど。中国では、ガルシア・マルケスがものすごく模倣されていたんです。それで向こうの授業で、『百年の孤独』は絶対に読めっていう話があって。それで日本から取り寄せて、日本語訳で読みました。そしたらすごく面白くて、逆に中国文学、これに比べたら全然面白くないんじゃないかっていうことに気付いて、絶望したんですよ、北京で。それで南米文学もどんどん読み出したら、めちゃくちゃ面白くて。たぶん私の感性に合っているんでしょう。南米文学がすごく面白かったので、それからスペイン語の勉強を始めて、原文で読めるようにして、南米に長期で旅行に行きました。
中地 つながっていくんだ。
橋本 はい。そういうつながりで広がっていきました。
 小澤 志木高の講師や、いくつかの大学非常勤を経て、現在、お茶の水女子大学の助教をして1年が経過しました。どうですか、今。
小澤 志木高の講師や、いくつかの大学非常勤を経て、現在、お茶の水女子大学の助教をして1年が経過しました。どうですか、今。
橋本 そうですね、もう年齢も年齢ですから就職したところで価値観が突然変わるわけではないので、同じようにやっていけたらいいなとは思っています。女子大なので、志木高ほどなんでも言っていいというわけではなかろうというところはあるんですけど。お茶の水女子大学は非常に小規模な大学なので、1授業に出る人数が非常に少ないんですよね。なので感覚としては、わりと高校の授業に近いようなかたちで、授業がしやすいところではあります。ただ、「全国から学級委員長が集まってくるような学校」って、この間、理事が言っていたんですけど、すごい真面目な雰囲気です。私も1年目でちょっと固かったというのもあって、志木高みたいに爆発的な盛り上がりというようなのはなかなか作れませんでした。去年の後半は大分ペースがつかめてきたかなっていうところです。今年は2年目なので、もう少し面白くやれるかなと思っています。
中地 担当している授業はなんですか?
橋本 純粋に語学の授業は1クラスだけで、あとは中国文学史、現代中国文学史や、中国文化論です。今年は言語と社会という授業がありますが、中国文学科の授業じゃないので、中国に関係ないことをやれるなと思っています。
著作と旅行体験について
小澤 講師の時から、すでに10冊ぐらい本を出しています。特に思い入れがある何冊かについて教えてください。
 橋本 一番記憶に残っているのは、やっぱり1冊目です。語学の習得法に関する本を書きました。本来はその言葉の面白さを伝えるような本を目指していました。基本的に一般向けの本は、自分が面白いと思っていることをほかの人にも面白いと思ってもらえるようにと思って書いています。最初はどうやったら本が出せるかよく分かりませんでした。持ちネタの中で一番出版社が話を聞いてくれるかなと思ったのが語学だったんです。語学習得っていう方向に寄せていけば、どこか出してくれるかなって思って、原稿を用意して、出版社に電話したり、原稿を送ったりして、出せることになった。1冊目が出た時が一番うれしかったですね。元々物書きというか、そういうことをやりたいと思っていたので。
橋本 一番記憶に残っているのは、やっぱり1冊目です。語学の習得法に関する本を書きました。本来はその言葉の面白さを伝えるような本を目指していました。基本的に一般向けの本は、自分が面白いと思っていることをほかの人にも面白いと思ってもらえるようにと思って書いています。最初はどうやったら本が出せるかよく分かりませんでした。持ちネタの中で一番出版社が話を聞いてくれるかなと思ったのが語学だったんです。語学習得っていう方向に寄せていけば、どこか出してくれるかなって思って、原稿を用意して、出版社に電話したり、原稿を送ったりして、出せることになった。1冊目が出た時が一番うれしかったですね。元々物書きというか、そういうことをやりたいと思っていたので。
あとは今も中心となっているのが「物語論」関係の本で、『ナラトロジー入門』が2014年に出て、ほぼ同じかたちで『物語論 基礎と応用』を講談社から出しました。「物語論」は当時としてはマイナーで、ほとんど一般には知られていない状況でした。分かりやすい本っていうのもあんまりなかったので、文学をやっている人でもちゃんとは知らない人が結構多かったんですよね。「物語論」の本を出すのは無理だと、いろんな出版社に断られました。最終的になんでも出してくれる水声社が出してくれたんですけど。講談社の『物語論』も、いや、これ絶対こんな本売れないだろうと思ってたので、うまいこと講談社をだませたなと思ったんですよね。こんなもの売れるわけないだろうと思ったんですけど、売れているんですよ。『ナラトロジー入門』ももう4刷まできましたし、『物語論』も7刷まできました。Twitterなんかでも、「物語論」ってワードで毎日誰かつぶやいているようになっています。以前はなかったことです。これは面白いよっていうのが世の中に広がったっていうのはうれしいですね。
中地 潜在的な需要があったのを掘り起こせたんだね。
橋本 そうですね。
中地 「語り」や「物語り」でいえば、言葉にしてもわからない世界が前提にあって、わからない世界をなんとか言葉にしよう、それを人とも共有しようということでしょ。それがどんな仕組みなのかわからないから、みんなそれを知りたいんだよね。
小澤 『ノーベル文学賞を読む』は一般向けに書かれていますが、志木高生にお薦めの作品があれば。
橋本 まずガルシア・マルケスは高校生で読んでも、物語の面白さが一番分かるものだと思うので、読んでもらいたいですね。あと、私の専門の中国文学だと、余華っていう作家が、全作品翻訳も出ているのでお薦めです。
やはり特定の作品というよりは、広く有名なものを手当たり次第、高校生のうちには当たってほしいなと思うんです。というのも、相性って確実にある。私はガルシア・マルケスが好きだけど、ガルシア・マルケス全然面白くないよっていう人も当然いるはずで、別のものがヒットする人もいると思うんですよね。何にはまるかは人によって違うので、できるだけいろんなものに出会ってほしいですね。そのリストは教員側がどんどん提示したほうがいいでしょうが。
中地 今は活字よりも小さい画面のゲームに夢中になっている高校生がほとんどだと思うんですけど、そういう高校生に対して肯定的な立場から見る場合、否定的な立場から見る場合、橋本さんはどんなふうに捉えますか?
橋本 文字を読む文化として、携帯のほうに流れているっていうのは、それは自然なことだとは思います。ただ、今の学生を見ていても、じゃあ昔より本を読む人が減ったかなっていうと、必ずしもそうでもないように思うんです。長いものを読む学生の絶対数が減ったかっていうと、どうでしょうか。昔は皆読んでいたかというと、私の同級生も別に読んでいなかったんでね。たぶん前の世代も読んでいなかったと思いますよね。一部の人は私の前の世代も読んでいたし、私の世代も読んでいるし、今の世代もやっぱり読んでいると思うんですよ。
中地 そこは一番大事なところね。だからテレビゲームやっていて、頭の中は空っぽっていうふうには思えない。
橋本 思わないです。古典とかも面白いと思う人の割合ってたぶんそんなに変わらないんじゃないかなと思うんですよね。でも出会わなければ面白いと思う人も思えなくなってしまう。やっぱり高校のうちに出会ってほしいなというふうに思います。
中地 そうですね。
小澤 読書と旅行体験と自分がしたい研究に、相関性はありますか?
 橋本 あります。好奇心というか、本の中で知ったこともありますが、実際に目で見て体験するのはまた違う知の喜びがあるので。旅行に行く前にそこの国の言葉を勉強して、現地の人と話して、いろいろ観察をして、ひどい目に遭って帰ってくるっていう、修業の一つのプロセスです。いろいろひどい目にも遭うんですけど、そこで得られるものとか、学べることってものすごく大きかったです。
橋本 あります。好奇心というか、本の中で知ったこともありますが、実際に目で見て体験するのはまた違う知の喜びがあるので。旅行に行く前にそこの国の言葉を勉強して、現地の人と話して、いろいろ観察をして、ひどい目に遭って帰ってくるっていう、修業の一つのプロセスです。いろいろひどい目にも遭うんですけど、そこで得られるものとか、学べることってものすごく大きかったです。
小澤 言える範囲でいいんですけど、旅行中、ひどい目に遭ったなとか、面白かったなって何かあれば。
橋本 私自身は意外と気を付けているので、大きいトラブルにはあってはいないんです。隣にいた人が窃盗に遭うとか、そのレベル。あとは、ペルーで白タクに乗っちゃったっていうのはありました。いきなり途中で言っていることが変わって、真っ暗なところに放り出されそうになりました。あれが一番怖かったかな。いろいろ間違えて、砂漠の真ん中で一人残されたこともあります。どうしよう、バスもないのにとなってヒッチハイクしたり。安い宿に泊まったがために南京虫にくわれたり。それも日本にまで連れてきてしまった。でもこれで南京虫のかゆさが分かりました。かゆい、本当にかゆい。
小澤 何匹もいたんですか、南京虫。
橋本 いや、くわれた痕はいっぱいあるんですけど、見えないんで何匹にやられているか分からないんです。
中地 皮膚にくっつけて持って帰ってきちゃったんですか?
橋本 たぶんそうだと思います。日本で繁殖したのかなと思ったんですけど、一緒に行った後輩から「橋本さん、体中ぼこぼこじゃないですか?」って電話が来たんです。その後輩が、先に皮膚科に行ったら南京虫らしいと。 それから、結構つらかったのはキューバで、何もない田舎町で持ってきた本もすべて読み切っているのにハリケーンが来て、3日間外に出られないっていうのがありました。元気なのに何もやれないっていうのは本当につらいんですよ。今もそうなんですけど、キューバって鎖国しているので、当然インターネットも使えないし、本当に何もすることがないんです。ハリケーンで停電しているし。その宿には私しか泊まっていなくて、後はおじいちゃんと犬がいるだけなんですよ。これはもう絶望的につらい。キューバではその前に食中毒になったんですけど、その次の町で3日間缶詰め。ハリケーンが去った翌日は晴れたんですが、日曜日。日曜日は交通機関がやっていないから移動ができない。その町にいた別の外国人観光客もフラストレーションを抱えていて、アメリカ人が開かない旅行社の扉をガンガン殴ってました。暇ってつらいんです。
中地 こればっかりは本当、業者の旅行のプログラムの中には絶対にないから。
橋本 絶対ない。安心なんですけどね、学校のプログラムとかで行った方が。逆にトラブルっていうのは、その時は本当に嫌ですけどね。キューバから帰る時は、この島沈んでしまえと思いましたけど、振り返ると本当、いい体験したなって思いますね。
仲間との「絆」と後輩へのメッセージ
小澤 志木高時代の仲間と、どんな付き合いがあります?
橋本 高校時代、一緒にやっていた友達とは今でも連絡して、年に1回会って、飲みに行ったりというのはずっと続いています。当時、文芸に興味があったんですけど、文芸部っていうのがなくて。勝手にそういうサークルみたいなのをやっていたんですね。その時にいたのが7、8人だったかな。集まって活動しているのか、していないのか分からないようなことをやっていたグループがあって。そのメンバーとは今でも続いていますね。
小澤 志木高時代の仲間だからこそといった「絆」はありますか?
 橋本 大学ってすごく大きいので、共有する体験って少ないんですよね。でも高校って同じ先生の授業受けて、同じところに旅行に行って、同じことをやっているっていう体験があるんで。その同じカルチャーというか、考え方っていうものを持っている中で話をするっていうのは、時がたっても楽しいです。年々、経年変化していく人生模様があって。なかなか結婚しないグループだったんですけど、その中でも皆、結婚してきて、子どもができてみたいなことになってきて。このまま一生続いていくんだろうなっていう感じはありますね。在学中にはそれほど親しくなくても、卒業してから会って、あの時同じ学年だったね、みたいなので話せたりとかっていうのは、やっぱり規模が比較的小さい学校ならではのいいところかなと思います。
橋本 大学ってすごく大きいので、共有する体験って少ないんですよね。でも高校って同じ先生の授業受けて、同じところに旅行に行って、同じことをやっているっていう体験があるんで。その同じカルチャーというか、考え方っていうものを持っている中で話をするっていうのは、時がたっても楽しいです。年々、経年変化していく人生模様があって。なかなか結婚しないグループだったんですけど、その中でも皆、結婚してきて、子どもができてみたいなことになってきて。このまま一生続いていくんだろうなっていう感じはありますね。在学中にはそれほど親しくなくても、卒業してから会って、あの時同じ学年だったね、みたいなので話せたりとかっていうのは、やっぱり規模が比較的小さい学校ならではのいいところかなと思います。
小澤 そうした仲間の連続の中に、教え子や新たな後輩たちも加わっていきます。どんな卒業生であってほしいですか?
橋本 大学に入っても志木高生ってちょっと変わっているとかって言われるところがあるんですけど、我々の自己認識としてはそんなに変わっているとは思っていなくて。むしろ我々のほうが普通ではないだろうかと思っているんですけど。そういうような何か価値観を一つに合わせるっていうんじゃなくて、好きにやれるっていうところがこの学校の一番いいところです。
さっきも言いましたけど、「この3年間がめちゃくちゃ楽しかった」って卒業した時に言えるような高校生活、今も送っている後輩をいっぱい見ていますけど、それ見るとやっぱり、今でもいい学校だなというふうに思えます。ここから先もそうであってほしいと思いますね。なお一層、特に文系の授業に関しては、なんだこの授業はっていうのがある学校であってほしいなと思っています。
中地 橋本さんが入ってきた時の驚きをまた、入ってくる生徒たちに必ず経験させられるように、我々が頑張らなきゃいけないですね。
橋本 そういえば、入学したての頃、本井先生の古典の授業で、最初に本井先生が教室に入ってきて、いきなり、「本井先生っていうのは神様みたいな人なんだけど、今は休職中だ」って言うんですよね。「俺は代わりのヤマグチって言うんだ」って言って、ずっとヤマグチの体でいくんですよ。そのうち、やっぱりあの人が本井さんだっていうことが1か月ぐらいして発覚するんですけど。本井先生はその遊びを3年に1回やっていて、3年後、ちょうど我々が卒業する年に本井先生に会ったら、「来年度また新入生を担当するから、偽名でいこうと思う」って言うんです。「今年はジャオキッソウでいこう」と。「そんな名前の人いますか」って聞きました。そしたら「ジャオっていうのは蛇の尾で、祖先は沖縄だ。キッソウは吉宗と書いてキッソウだ」って言うんです。そんな名前の人いますかって思いますよね。この名前、裏返すとウソツキオヤジになるんです。3年後輩がいたんですけど、その後輩が4月に「本井先生、休職中らしいんですよね」って言ってて。「ジャオさんっていう人なんですよ」って言ったから、だまされているなと思って。
中地 おかしかったね。
橋本 面白かったですね。あの遊び、なんのためにやっていたのかは、ちょっと分からないですけど。
中地 それ、何かのためじゃないんだよね。
橋本 何かのためじゃない。
中地 なんのために勉強するかっていうこと自体を超越していくためにやっていたんだよね、きっとね。勉強そのものが面白くなれよっていうメッセージだと思うよ。何かのために勉強しているんじゃないんだよ、君たちは。
橋本 何かのために勉強しているんじゃない。
所属は2019年4月現在
 )
)