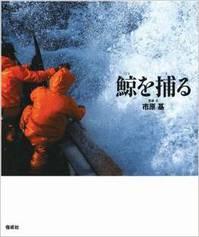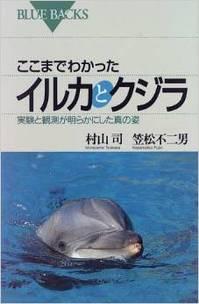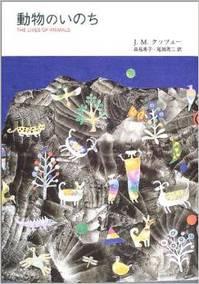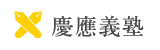クジラの本(書評)
鯨を捕る
著者名:市原 基
出版社: 偕成社
出版年: 2006年
この本は、写真家、市原基さんが1982年に捕鯨船に同乗し、南極の海でぶつかり合う生命と生命を写真に収めた記録である。実際に捕鯨船に乗り合わせた人による解説なので「実際の捕鯨」がどのようなものであるかが分かる。
この本によると、捕鯨が行われる南氷洋までは日本から片道13000キロであり、約1か月の航海になる。捕鯨には3つの船が使われる。それぞれ母船、キャッチボード、仲積船と呼ばれ、キャッチボードは小型で鯨をしとめる用、キャッチボードがとってきた鯨を解体するのが母船、荷物を運ぶのが仲積船である。これらには300人以上の乗組員がそれぞれの役割に就いて働いている。
鯨の話をすると「鯨を殺す」という結果に重点が置かれがちだが、この本ではそれまでの漁師の苦難の過程が写真とともに説明されていて新しい発見ができる。300人を超える乗組員が出発の際に、親族をはじめとした多くの人々に見送られる写真を見ると、それが彼らの生業であるということが生々しく伝わってくる。
クジラ&イルカ生態ビジュアル図鑑
著者名 水口博也
出版社 誠文堂新光社
出版年 2013年
君はクジラとイルカについてどのくらい知っているかな?例えば種類。クジラならシロナガスクジラ?マッコウクジラ?イルカならバンドウイルカ?でも、クジラとイルカはそれだけじゃないよ。この本には83種類のクジラ・イルカが見易いカラー写真で載っているんだ。クジラとイルカのこと、何も知らないけど興味がある・・・、もっと知りたい!なんていう君はぜひこの本から読んでみよう。今まで知らなかったクジラとイルカ達の世界を覗けるぞ。
また、写真で見るだけじゃ満足出来ない!なんていう君。ホエール・ウォッチングに興味はないかな?もしもホエール・ウォッチングをしたくなっちゃっても心配ご無用。この本では日本でホエール・ウォッチングが出来る場所とホエール・ウォッチングで必要な道具を教えてくれている。行きたい場所を決めて道具をリュックに詰めたら、さぁクジラ・イルカを見に海へ繰り出そう!
この本を読んでホエール・ウォッチングに行けばもう君はクジラ・イルカ博士。友達に知識をひけらかそう!
イルカ‐生態、六感、人との関わり
著者名:村山 司
出版社:中公新書
出版年: 2009年
私が夏の研究テーマで調べたのは『人とクジラの関わり』についてだったのだが、クジラだけではなく、イルカとの関わりについても調べた時にこの本を参考にした。特に人との関わりについて書かれた部分を中心に本を読んだのだが、日本人のイルカ観の移り変わりやイルカと人との新たな関わり方の可能性が描かれていて、たいへん興味深い内容であった。
自分たちにとってイルカは生まれた時から親しみやすいイメージが強かったが、このイルカ観は私たちが生まれる前の1990年代初頭に打ち立てられたものだという。「食料」から「スター」へとイルカに対する認識が変わっていった。そもそも昔はイルカの知名度が低かったという事実は意外であった。これらの日本人のイルカ観の変化を踏まえた上で、イルカは友であり、また、一方では漁を邪魔する敵でもあるということが書かれていたが、これに関しては両者の立場を踏まえた上でよく考えていかなければならないと思った。 この本ではイルカについての情報がイルカ漁に賛成、反対関係なく中立的な立場で書かれているので、イルカについて考える入門書としてピッタリではないか。
白人はイルカを食べてもOKで日本人はNGの本当の理由
著者名 吉岡逸夫
出版社 講談社+α新書
出版年 2011年
私が今回紹介する本は「白人はイルカを食べてもOKで日本人はNGの本当の理由」という本だ。この本は青年海外協力隊の一員として活動した後、世界60か国をまわり取材し現在は中日新聞新宮局長として活躍されている吉岡逸夫氏が一年半の期間を経て取材、体験した現代の捕鯨の実態をわかりやすくまとめた一冊になっている。
私がこの本の中でとくに面白いと思った点は、一般人ではなかなか取材までたどりつけない専門家や反捕鯨団体シーシェパードの幹部とのインタビューの場面だ。その中でも吉岡氏が何度も交渉し、一年かけて取材に成功した太地町いさな会のメンバーの一人、脊古輝人氏との対談は特に印象に残るものだった。脊古氏の人生と鯨漁の密接なかかわりを吉岡氏が少しずつひも解いていく中で見えてきた、長年太地町で漁師として活躍し町の歴史を知っている脊古氏だからこそ語ることができる現在の捕鯨に対する見解はとても貴重なものだった。製作に携わったリチャード・オバリー氏はもちろん、現在も捕鯨を行っているフェロー諸島での取材なども詳細に記されている。
イルカを食べちゃダメですか? ~科学者の追い込み漁体験記~
著者名:関口雄祐
出版社:光文社新書
出版年:2010年
捕鯨問題にはどうにも解決できない部分がある。本書では、それらの問題に対する筆者の意見が多く述べられている。例えば、日本人は食べ物を食べるとき、「いただきます。」と言う。これは生き物の命をいただく(食べる)ことへの感謝を表している。欧米人はそれとは違い、主(神)に祈りの言葉を捧げる。このような価値観の違いによる論争は、解決の糸口がない。唯一あるとすれば、お互いの考えを理解し歩み寄ることだろう。本書はこのように我々に知識を与え、捕鯨問題に対する見方をガラッと変えてくれる。
本書には、このような言葉がある。「『日本には捕鯨文化がある』と『捕鯨は日本の文化である』とは違いが大きい」。前者は世界にも捕鯨文化はあり、国という単位ではなく地域に主体を置いた物言いで、後者は、捕鯨文化は日本固有のものだと主張しているようである。言い方ひとつで印象は大分変ってくる。見方を変えるとこんなにも違って見えるのだ!
また、本書の前半では元水産庁調査員のイルカの研究者が、太地町で15年間にわたり、イルカ追い込み漁の漁船に何度も乗せてもらった経験が語られている。イルカを含めたクジラ類と太地町との400年以上にわたる関わりを、捕鯨方法から解剖、食肉流通まで多方面から書いている。漁師の人たちの生活を知りたい人や、少数民族文化について論じたい人はこの本を読むと、さらに考えが深まるだろう。
この本は様々な方向から捕鯨問題を考えている。捕鯨問題入門書としても読める本書をぜひ読んでみてほしい。
ここまでわかったイルカとクジラ―実験と観測が明らかにした真の姿
著者名 村上司 笠松不二男
出版社 講談社
出版年 1996年
この本で最も興味深かったのは1部の3章「イルカの社会行動」で挙げられているイルカの社会的行動である。この本には"群れ"という社会に属するイルカの様々な興味深い行動が記されている。特に興味深かった例を2つ挙げることにする。1つ目は、子と母の繋がりである。子イルカは出生直後、水面まで泳いでいき呼吸しようとするが、親イルカは子供を水面までおしあげてやるなど、甲斐甲斐しく子供の面倒を見る。2つ目はイルカの群れに乳母の役割を果たすイルカが存在するということである。イルカの群れには母イルカの他に、育児を補助する年長の雌のイルカが存在する。これらのイルカはちょうど乳母の様に、出産の時だけでなく育児の手伝いもする。出産直後の母イルカのへその緒を噛み切る習性も確認されている。
この本の冒頭で著者は、イルカやクジラを神格化することや特別視することをせず、科学的根拠に基づいたイルカとクジラの能力と生活について知ってもらうことがこの本の意図だと述べている。この本の内容はまさしくその意図にかなっており、群れという社会に存在するイルカやクジラのありのままの姿を捉えている。そこがこの本の魅力である。
全集―日本の食文化第4巻 魚・野菜・肉
芳賀登・石川寛子監修
出版社: 東京:雄山閣
出版年: 1997年
私が今回紹介するのは、芳賀登・石川寛子監修『全集―日本の食文化第4巻 魚・野菜・肉』の中の柴田恵司「肥前『鯨組』絵巻と捕鯨の盛衰」だ。この本では、日本の食に関する歴史や具体的な料理などが紹介されていて、「肥前『鯨組』絵巻と捕鯨の盛衰」では「鯨組」と呼ばれる江戸時代の大規模な捕鯨集団を中心に日本の江戸時代までの捕鯨について説明している。
今回、特に面白いと感じ興味を引かれたのは、日本最古の捕鯨資料として登場した『西海鯨鯢記』に記載されている鯨料理についてである。ここでは今から三百年以上前の江戸時代に作られていた鯨料理の紹介がされており、調理法が主に記されている。例として、鯨肉のすき焼きのようなものや鯨のステーキなど様々な料理が紹介されている。私は、これらの料理を知って日本にどれほど前から鯨肉を楽しく食する文化があったのか垣間見ることが出来た気がした。
この本では、捕鯨に関することはもちろん、日本のあらゆる食材に関する歴史が記されている。日本に古くからある食材や料理に興味がある人はこの本をぜひ手にとってみてほしい。
動物のいのち
著者名: J.M.クッツェー
出版社: 大月書店
出版年: 2003年
捕鯨問題を考える上で西洋に対する理解は欠かせない。だが、私たちは漠然と環境を破壊する文明という面と過激な自然保護を主張するという面でしか西洋を理解していないような気がする。
本書は、ノーベル賞受賞作家であるJ.M.クッツェーの動物のいのちに関する講演の記録をクッツェー自身が小説形式にしたものである。
クッツェーは南アフリカで白人の子として生まれた。その出自のせいか西洋という文明に属しながら、それを外から見る目を持っている。
クッツェーは小説の中では、エリザベス・コステロという女流作家として登場してくる。コステロは、ホロコーストなどを引き合いに出して動物に対しても共感することの必要性を主張する。人間に共感することは出来るのに、なぜ動物にはしないのかと投げかけ、「共感的想像力には限界はないのです。」と述べたのは印象的だった。
しかし、コステロの思いは理解されない。それはなぜか?
コステロ自身もよく分からない。それが何故なのかは、本書の重要なテーマの一つであり捕鯨問題とも重なる点である。
一人ひとり考え方は違うはずなのに規模が大きな話になるとそう考えなくなる。いろいろな考えがあり理解されないことが必ずある、動物のいのちに関する議論は少なくとも論破することを目的としていない。では、なぜ人は議論するのか?そんなことを考えさせられる一冊だった。
 )
)