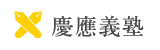報道から見る捕鯨裁判
裁判について
南極海における捕鯨事件(なんきょくかいにおけるほげいじけん、英語:Case concerning Whaling in the Antarctic、フランス語:Affaire du Chasse à la baleine dans l'Antarctique)とは、日本による第二期南極海鯨類捕獲調査(以下JARPA II)の国際法上の是非を巡って、2010年5月31日にオーストラリアが日本を国際司法裁判所に提訴した国際紛争である。日本が国際司法裁判所の紛争当事国となる初めてのケースであり、3年間におよぶ提訴内容の調整を経て、2013年6月に口頭弁論が開始された。2014年3月31日に本案判決が下され裁判は終了した。その内容は日本にとって全面敗訴に等しいものとなった。(wikipedia「南極海における捕鯨事件」より引用。urlは以下参照)
参考:判決文...http://www.icj-cij.org/docket/files/148/15951.pdf
Wikipedia「南極海における捕鯨事件」閲覧日2014年12月25日...
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%B5%B7%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%8D%95%E9%AF%A8%E4%BA%8B%E4%BB%B6
国際司法裁判所 判決文
以下は国際司法裁判所による判決文である。
WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND INTERVENING) (国際司法裁判所 2014/3/31)
91. First, Australia acknowledges that Article VIII, paragraph 2, of the Convention allows the sale of whale meat that is the by-product of whaling for purposes of scientific research. That provision states:
(第一に、(国際捕鯨取締)条約の第8条2項が科学的研究を目的とする捕鯨の副産物である鯨肉の販売を許容しているということは、豪州は認めている。)
However, Australia considers that the quantity of whale meat generated in the course of a program for which a permit has been granted under Article VIII, paragraph 1, and the sale of that meat, can cast doubt on whether the killing, Taking and treating of whales is for purposes of scientific research.
(しかし、豪州が考えるに、条約第8条1項のもとで特別許可書が付与されたプログラムによって出てきた鯨肉の量と、その鯨肉の販売が、鯨の殺傷、捕獲と処理が科学的研究を目的とするものであるかどうかについて疑問を投げかける余地がある。)
94. As the Parties and the intervening State accept, Article VIII, paragraph 2, permits the processing and sale of whale meat incidental to the killing of whales pursuant to the grant of a special permit under Article VIII, paragraph 1.
(当事国および訴訟参加国が受け入れているとおり、条約第8条2項に基づき、第8条1項のもとで付与された特別許可書に基づき殺された鯨の付随的な鯨肉の加工と販売は認められている。)
In the Court's view, the fact that a program involves the sale of whale meat and the use of proceeds to fund research is not sufficient, taken alone, to cause a special permit to fall outside Article VIII.
(裁判所の見解では、鯨肉の販売及び右を調査の原資としている事実のみをもって、特別許可書を第8条の枠外に置くことにはならない。)
Other elements would have to be examined, such as the scale of a programe's use of lethal sampling, which might suggest that the whaling is for purposes other than scientific research.
(プログラムにおける致死的サンプリングの使用の規模といった、捕鯨が科学的調査以外の目的であることを示すかもしれない他の要素が検討されなければならない。)
In particular, a State party may not, in order to fund the research for which a special permit has been granted, use lethal sampling on a greater scale than is otherwise reasonable in relation to achieving the program's stated objectives.
(特に、締約国は特別許可書が付与された調査の資金とするために、定められたプログラム上の目的達成との関係で合理的な範囲を超える規模の致死的サンプリングを用いることはできないだろう。)
(和訳は、外務省のサマリー仮訳を参照しつつ、日本報道検証機構による)
以上の文は以下のサイトのものである。
日本報道検証機構goohoo2014年5月31日 「鯨肉販売は違反」 国際司法裁判決の解説に誤り
http://archive.gohoo.org/alerts/140531/
判決後の捕鯨に関する主なニュース
(情報源:朝日新聞デジタルにて「捕鯨」で検索し抜粋、閲覧日2014年12月9日
http://sitesearch.asahi.com/.cgi/sitesearch/sitesearch.pl?Keywords=%E6%8D%95%E9%AF%A8&Searchsubmit2=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&Searchsubmit=%E6%A4%9C%E7%B4%A2)
2014年
4月(記事数:44)
1日 農水相、南極海捕鯨中止表明
楽天、ネット通販にて鯨類の肉の販売を禁止
4日 自民議連が首相に調査捕鯨再開への取り組みを要請
5日 南極の調査捕鯨団、帰国
8日 2013年度の調査捕鯨、捕獲数は251頭と発表
15日 日本鯨類研究所が来年度以降調査捕鯨を再開する意思を明らかに
17日 北西太平洋での調査捕鯨、開始予定日延期と水産庁が表明
18日 政府は北西太平洋での調査捕鯨を捕獲頭数を減らし実施すると決定
26日 北西太平洋での調査捕鯨開始
27日 北西太平洋での調査捕鯨にて1頭目のミンククジラ水揚げ
29日 太地にて「鯨供養祭」
5月(記事数:6)
1日 ミンククジラ、初競り
15日 オーストラリア人女性、「捕鯨反対の外国人」という理由で入館を拒まれたとして太地の「町立くじら博物館」を提訴
31日 日本海捕鯨、函館で初水揚げ
6月(記事数:9)
20日 千葉のツチ鯨漁、解禁(判決後初の沿岸捕鯨)
7月(記事数:2)
12日 南房総、和田浦にて「捕鯨裁判」をテーマに勉強会
22日 山口、長門にて「通くじら祭り」
8月(記事数:3)
15日 三重県四日市市鳥出神社にて「鯨船行事」
28日 太地町にて、反捕鯨団体などへの対応を協議する「環境保護団体等対策合同会議」
9月(記事数:23)
1日 太地町にてイルカ追い込み漁解禁
2日 政府は南極海での調査捕鯨の捕獲対象をミンククジラのみに絞る方針を明らかに
7日 釧路沖での調査捕鯨でミンククジラの1頭目水揚げ
15日 スロベニアにて国際捕鯨委員会(IWC)総会開催
17日 太地、ゴンドウ鯨初水揚げ
18日 IWC総会にて、南極での調査捕鯨を再開する方針の日本に対し再開の先延ばしを求める決議
24日 房総捕鯨発祥の地勝山で「クジラまつり」
10月(記事数:1)
30日 自民党、捕鯨対策特別委員会を発足
11月(記事数:5)
18日 政府は南極海調査捕鯨の捕獲対象はミンククジラのみ、また捕獲数は333頭という新計画案を表明、IWCへ提出
4月の記事の数は44と判決後今までで一番多く、内容としては国際司法裁の判決とその影響を受けたものが主である。次に多いのは9月の23で、これは太地のイルカ漁解禁とIWC総会、それに関連したニュースで多くなったのである。
つまり、判決後の4月の記事数は映画「ザ・コーヴ」で有名な太地町のイルカ漁解禁と捕鯨を管理しているIWCの総会がある月の約2倍となっており、ここから調査捕鯨がなくなることは、それほどの影響力を持っていると言える。
毎日新聞の反応
以下、毎日新聞 2014年04月01日 東京朝刊より引用
http://mainichi.jp/shimen/news/20140401ddm002040116000c.html
『調査捕鯨:南極海の調査捕鯨中止 捕鯨政策見直し必至 消費影響は限定的』
国際司法裁に詳しいアッサー研究所(ハーグ)のリベリンク・上席研究員(国際法)は「予想以上に厳しい判断。科学調査といいながら研究成果が乏しく、なぜ、何のために、いつまでやるのか、透明性、明確性が欠けていた」と分析する。
判決は、科学調査のため例外的に捕鯨を行うことまでは否定せず、日本の調査捕鯨も「科学目的と性格づける調査も含まれている」と指摘した。しかし▽87年から04年までの第1期調査と第2期調査の違いが明確でない▽非殺傷調査を増やす検討をしていない▽目標枠に比べミンククジラの捕獲量が少ない▽ナガスクジラの捕獲量も科学調査には不十分▽期限が切られていない−−として「科学調査ではない」と断定した。
科学調査であることが証明できない結果、商業捕鯨とみなされ、86年からの捕獲一時停止(モラトリアム)に違反するなどと判断されて全面敗訴となった。
判決の不当性について
捕鯨政策の見直しは必至との記事だが、判決の不当性について指摘するべきだと思う。
ICJの判決の一つに「国際的な研究機関との協力が欠如している」とあるが、これが最も疑問に思う点である。なぜなら日本は調査計画を国際捕鯨委員会に提出して、決められた種類を決められた頭数だけ採取しているからだ。それに種の保護という点において協力するかどうかは各国の判断でいいと思う。南極海は公海だからだ。そもそも日本は調査捕鯨の研究成果について公開しているし、日本は絶滅危惧種の保存・保護にも尽力しており、国際捕鯨取締条約ICRWの目的にも合致している。
他にもICJの判決に「研究結果が限られているため」とあったが、果たしてそうだろうか。絶滅危惧種と言われる鯨だが、減少する鯨種の中にも増える種類もある。鯨が増える事で海の生態系がどの様に変化するのかを調べる必要もある。鯨捕獲して殺す理由は、主に鯨の年齢、餌の種類を調べる為だ。仮に鯨に嗜好性があったとしたら将来他の鯨や魚がどうなるのか。このようなことを予測し生態系のバランスが崩れない様に管理しないといけない。研究結果が限られているなどということはない。その結果として日本の調査捕鯨は,2006 年の科学委員会で鯨類学に大きな貢献をなしたとして高く評価されたのではないのか。(条約第8条による特別科学許可)
判決の考察
判事の私的感情の介入について
裁判と言うものは本来私的感情を抜きにして公平にものを見ることが必要とされる。しかし、今回の裁判ではそれが行われていなかったということが『月刊正論』2014年6月号、308ページの「反捕鯨国を勝たせた国際司法裁判決の不合理」(八木信行著)という記事で以下のように述べられている。
「判決は16人の判事の投票で決まったが、判決賛成は12人で反対はわずか4人であった。判事の出身国が捕鯨支持であるか否かにかかわらず、法律的な解釈だけで決着すると想定していた。しかし判決文とは別に公表された各判事のコメントを読むと、中には『ほかの判事とは違って自分はクジラに特別な感情を有していないので反対票を投じた。』などといった記述も見られる。」
この通り、この判事の発言から彼らが「クジラに対する特別な感情」を有しているか否かがその票数に影響を及ぼしていることが分かる。
評価会について
『月刊正論』同号によると、「IWC 科学委員会では、南極海の第2期プログラムを評価する会合を今年2月に開催」し、「この科学的な報告書がすぐに出るはずであったが、ICJはそれも待たずに判決を出し」た。ICJの公平な判決をしようという意欲が見られない行動である。
シーシェパード と判決の関連について
過激な反捕鯨運動で名の知られているシーシェパードであるが、その行動に日本は何度も頭を悩ませている。今回の調査捕鯨にも彼らの妨害行為が影響を与えており、『月刊正論』同号ではこう述べられている。
裁判では、日本側が、調査捕鯨船に対するシーシェパードの過激な妨害行為についても説明し、そのために計画が予定通り遂行できなかったと主張していた。しかし、判決は、状況に合わせて日本が調査計画を臨機応変に変更していない点を問題とした。状況変化を作り出したシーシェパードの側ではなく、対応を強いられた日本側に責任が転嫁されたと言えるだろう。
ICJの「調査捕鯨は科学的でない」という主張について
調査捕鯨というものは、商業捕鯨を禁止されてしまった日本がそれが生態系に影響を及ぼさないということを証明するために各鯨類の個体数などを調査するものである。その標本数は非常に厳格な科学的根拠に則って決められている。
2014年5月28日『日刊水産経済新聞』「科学者から見た国際司法裁判決」の記事によると 、日本側は調査期間を「6年間」と定め、クロミンククジラに対する調査項目は「性成熟年齢・妊娠率・脂皮厚・DNA解析資源量を勘案し」、標本数を「850頭」とした。しかしICJはこれらを「標本数の科学的根拠が弱い」「非科学的な理由で過大な頭数に決めた」と判断し、今回の判決に至った。科学者たちはこれに対し、「鯨類の専門家による調査の妥当性は明らかに認められており、報告書はIWCホームページで公開された公式なものである」「科学的専門性からみて、ICJ判決が的外れであると言わざるを得ず、判決が恣意的に『捕獲調査を悪意を持って疑似商業捕鯨』と決めつけた」と批判をしている。
このように、今回のICJの判決には多くの不合理性と矛盾が見られるため、追求の余地が大いにある。そのうえ、今回はこのままの第2期南極海鯨類捕獲調査(JARPAⅡ)のプログラムでの調査捕鯨は控えるようにと判決されただけであり、この内容を改定することで日本は再び調査捕鯨を継続することが出来るのである。そのため、決して「敗訴」などという言葉ひとつで表してよいことではない。 なぜ彼らはこれを「敗訴」ということのみを報じたのか。それは、日本国民が捕鯨問題に関心が低く、この情報を提供するためには、日本が裁判で負けたということのみを伝えるだけで十分だと判断したからではないか。
 )
)