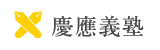「大川小学校津波裁判から学ぶもの」
 2024年7月12日(木)、弁護士の齋藤雅弘先生を慶應大学三田キャンパスにお迎えし、第136回志木演説会が行われました。齋藤先生は、東日本大震災の際に起きた宮城県石巻市立大川小学校津波被害事件の原告側代理人弁護士のおひとりです。
2024年7月12日(木)、弁護士の齋藤雅弘先生を慶應大学三田キャンパスにお迎えし、第136回志木演説会が行われました。齋藤先生は、東日本大震災の際に起きた宮城県石巻市立大川小学校津波被害事件の原告側代理人弁護士のおひとりです。
2011年3月11日、大川小学校では本震後の津波により、グラウンドで待機させられていた児童70名の命が失われ、今もまだ4名の児童が行方不明となっています。また同時に教員10名も犠牲となっています。残されたご遺族は、最終的に訴訟という形をとったわけですが、齋藤先生は原告側代理人弁護士として吉岡和弘弁護士と二名で、ご遺族と共に裁判を闘われました。
講演は、
1.なぜ、大川小学校では未曾有の犠牲者を出してしまったのか?
2.大川小学校の児童の遺族が裁判(訴訟)を提起しことの意義と社会の受け止め。
3.この裁判では何が判断され、どのような結論が出され、それは社会の制度や仕組みの中でいかなる意義があるのか。
豊富なスライド資料と共に、以上3点を軸にお話しいただきました。
齋藤先生らは、国家賠償訴訟という大変複雑な訴訟をたった二人の弁護士で闘い抜き、事実上の勝訴まで原告を導かれました。特に仙台高等裁判所が出した控訴審判決は、日本社会に対する大きな警鐘となる画期的なもので、その意義はとても大きなものと言えます。同判決では、本件は震災当日の現場教員の過失(現場過失)によるものではなく、地震が発生する以前(平時)における備えの不十分さ(平時における組織的過失)が原因であると断定されました。つまり、備え(避難マニュアルの整備など)が法規通りしっかり行われていれば、現場教員が迷うことなく行動ができ、結果として生徒らの命はことができた、ということです。
平時における事前準備の大切さ、必要性は、学校はもちろんですがそれ以外にも広がりを持つ視点です。講演後には、この裁判が日本の制度や仕組みの中でいかなる意義があるのか、という点についても生徒からの質問があり、真摯にお答えいただきました。
この講演を聞いた3年生は、9月に実際に現地を訪ね、ご遺族から直接お話を伺いながら震災遺構大川小学校を見学できました。2年生と1年生の生徒は、3年生の秋になれば見学旅行で現地を訪ねることになるでしょう。その時、このお話を思い出し、現地に立ってもらいたいと願っております。
 )
)