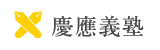2024年12月12日(木)、三田キャンパス西校舎ホールにて、第137回志木演説会が開催されました。慶應義塾塾長の伊藤公平先生を講師としてお招きし、「科学技術でより良い社会を築けるか」という演題でお話しいただきました。当初は「量子コンピューター」という演題の予定でしたが、量子コンピューターがどのような未来をもたらすかという可能性をさまざまな切り口から提示され、ChatGPTに代表される科学技術の急激な進歩に対して、自身の研鑽やその技術利用の目的の自己検証の必要性を強調されるという、普遍性の高い、わかりやすい内容でお話しいただきました。
導入は、イーロン・マスク氏が作成した、ロボット・コンピュータ・テクノロジーの発展を予測した映像の紹介から始まりました。その中で、スパコンの性能が半導体のダウンサイジングに制約されることを説明され、原子1個でオン・オフを可能にできるようになる未来(2030年前後)が直近に迫っていること、それをブレイクスルーするための解が、「使い方」であるAIおよび「技術」である量子コンピューターであることを話されました。AIは優秀である一方、選択肢が膨大に存在する「最適化問題」が苦手であり、これに対して量子コンピューターは、コンピューターの演算の基礎にある二進法の1か0かの可能性を同時に内包できることで乗り越えることができるとのことです。既に慶應義塾大学では複数の企業と連携し、金融ビッグデータの解析を量子コンピューターで行っており、経済予測の道筋をつけようとしています。現在の量子コンピューターは技術的にはまだ幼稚園レベルの成長段階にありますが、医療分野において腸内細菌のビッグデータを解析するなどの蓄積を続けていて、技術的に成長しているそうです。
量子コンピューターの進歩に合わせて必要なことは、悪用しない仕組み作りであり、慶應義塾ではAIをモデルに3つの取組みを始めているそうです。一つは「使い方」の問題で、日吉生成AIラボでは、塾生が塾生を教える仕組みの中から、より適切なAIの使い方を模索すること、二つ目に「AI自体の開発」をカーネギーメロン大学と最先端研究として進めているとのこと、三つ目に「AI時代における人間の尊厳の定義」をX Dignity Centerにて、憲法学者、経済学者らと研究を進めているとのことです。
これらのことを考えていく上で、経験(歴史)を総合することで最善策を判断し、求めていく姿勢が重要であることを強調されました。そのために、志木高生に対し、多くを学び、世界を知ること、積極的に留学を考えることなどを勧め、話を閉じられました。
質疑応答では、X Dignity Centerの働きに絡め、「『社会の正しさ』をどのような尺度で測ればよいか?」、「人間、AI共にそれぞれ問題を抱えているが、双方が折り合いをつけるべきところはどこか?」などの質問が出され、多くの生徒が熱心に聞いていたことが伺えました。
演説会終了後、自由選択科目「芸術A」の履修生徒29名による合唱が披露され、「ふるさと/嵐」、「僕らはいきものだから/緑黄色社会」、「その先へ/山崎朋子」の3曲が歌唱されました。その後、国際交流に参加した生徒から、台湾、フィンランド、オーストラリアそれぞれの交流の内容が紹介され、現在、オーストラリアのToowoomba Grammar schoolから本校に来て、まもなく帰国する二人の留学生から、日本語で挨拶を頂きました。
次の志木演説会は、2025年7月中旬を予定しています。
 )
)