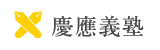3年生は9月24日(火)から9月27日(金)まで、3泊4日で東北地方へ見学旅行に行きました。今年で3年目となります。初年度と昨年度の行程を踏まえ、新たな訪問先もあります。
3年生は9月24日(火)から9月27日(金)まで、3泊4日で東北地方へ見学旅行に行きました。今年で3年目となります。初年度と昨年度の行程を踏まえ、新たな訪問先もあります。
1班(ACF組)は東北新幹線を一ノ関駅で降りて花巻・南三陸・仙台・山形県を巡る行程で、2班(BDE組)は山形新幹線を山形駅で降りて1班と逆回りの行程です。以下、2班を中心に報告をします。
初日、新幹線を山形駅で降りて貸切バスに乗車し、ふもと屋で昼食をとって宝珠山立石寺へと向かいました。松尾芭蕉の俳句「閑さや岩にしみ入る蝉の声」で知られていますが、木々に囲まれた長い長い石段を登り切りますと絶景が広がっています。名物のアイスクリームに舌鼓を打つ者もいれば、川まで降りて水遊びに興じる者もいて、ゆったりとした時間を堪能していました。その後、斎藤茂吉記念館に移動し、近代日本を代表する歌人への理解を、数々の肉筆資料や豪快なバケツの使用法など、館員の興味深いお話によって深めておりました。その後はバスで仙台に移動し、班ごとに市内で自由に夕食をとり、仙台市内のホテルに宿泊をしました。
2日目は朝から夕方まで仙台周辺での班別自主研修です。行先は仙台城跡、瑞鳳殿、各博物館などの仙台市内、あるいは松島・秋保温泉に足を延ばすなど班により様々で、あらかじめ作成した計画に沿って行動をしました。15時半に宿泊した仙台のホテル前に集合をして、バスで南三陸へ向かいました。この日は、1班と2班が合流し同じホテルでの宿泊となり、にぎやかでした。
3日目、午前中に志津川湾・波伝谷漁港から漁師さんの漁船に乗せて頂いて養殖の様子を見学する予定だったのですが、あいにくの雨で中止となり、雨天用に計画していた漁師さんによるロープワーク指導と蠣を加工する作業をめぐる講話となりました。真面目に学びつつ、作業場にいた人懐こい猫に夢中になる生徒が多かったです。その後は南三陸町自然環境活用センターに移動し、志津川湾の生態系への地球温暖化による影響、持続可能な漁業の実践の講義を受けました。多くの生物の標本があり、くぎ付けになっている生徒もいました。
南三陸町防災対策庁舎跡の前で手を合わし、南三陸さんさん商店街での自由昼食後、昨年に続き、石巻市震災遺構・大川小学校を見学しました。 大川小学校は東日本大震災後の津波で児童108名中74名・教員10名が亡くなった学校で、校舎などが当時の形で保存されています。7月12日に志木演説会で大川小裁判に携わった齋藤雅弘弁護士の講話に全生徒が耳を傾けており、また、選択科目「社会C」の授業でも大川小学校のことを扱っております。クラスごとに3グループに分かれて3人のご遺族の方から直接お話を伺う大変貴重な機会を得ました。それぞれの方のご経験に基づくたくさんのお話をしていただきました。それぞれのクラスでうかがったお話を自分事として受け止めるように促して下さいました。各自が、大切なことを学んだようです。
4日目は、まずは岩手県の花巻で宮澤賢治に関わる史跡や記念館を回ります。昨日は夕食時に伝統芸能「鹿踊り」を鑑賞しましたが、賢治の童話集『注文の多い料理店』にも「鹿踊りのはじまり」という童話が収録されています。宮沢賢治記念館(希望者はさらにイーハトーブ館)、「雨ニモマケズ」詩碑、賢治が耕した「下ノ畑」、イギリス海岸、賢治が暮らした羅須地人協会の建物と、まさに生徒たちは「銀河鉄道の夜」のジョバンニとカムパネルラのように関係する地を巡っていきました。
昼食後、中尊寺を参拝、金色堂などをじっくり拝観し、松尾芭蕉の俳句「夏草や兵(つはもの)どもが夢の跡」に想いを馳せながら、新幹線で帰途につきました。3年生にとっては最後となる旅行でしたが、すでにコロナ禍のような制限は一切なく、日常と異なる時間を、かけがえのない仲間たちと満喫していました。
 )
)