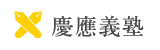7月30日(水)から8月24日(日)にかけて、本校の3年生2名がオーストラリア・クイーンズランド州にある Toowoomba Grammar School(トゥーンバ・グラマー・スクール、以下TGS) にて、約4週間の国際交流プログラムに参加しました。
7月30日(水)から8月24日(日)にかけて、本校の3年生2名がオーストラリア・クイーンズランド州にある Toowoomba Grammar School(トゥーンバ・グラマー・スクール、以下TGS) にて、約4週間の国際交流プログラムに参加しました。
TGSは、ブリスベンから内陸に約125キロの場所に位置する、歴史と伝統を誇る私立男子校で、本校とは2012年から交流があります。3〜4週間の長期プログラムは、今年で8回目の実施となりました。
日本の夏休みはオーストラリアでは冬にあたり、現地は第3学期(Term 3)の授業期間中です。生徒たちはホストブラザーとともにTGSの授業に参加し、放課後や週末には、TGSの一大イベントであるラグビーの対抗戦を応援するなど、さまざまな形でオーストラリアの文化や学校生活を体験しました。今回、2名のうち1名はホストファミリー宅でホームステイを行い、もう1名は学校内の Boarding House(寄宿舎)に滞在しながら、週末はホストファミリーと過ごしました。
また、滞在中の8月1日には教職員訪問団とともに「Study Abroad Partnership Declaration(留学協定書)」の調印式に出席し、8月5日には TGS創立150周年記念式典にも参加しました(詳しくはこちら)。
来る11月末からは、2名のTGS生徒が本校を訪問し、ホームステイを通じて交流を深める予定です。今後も、より多くの志木高生とTGS生がこのプログラムに参加し、友情を育んでいくことを期待しています。
Toowoomba Grammar Schoolとのプログラムに参加した生徒の体験記(抜粋)
今回のオーストラリアでの寮生活は、出発前の想像以上に多くの学びや気づきを与えてくれました。特に持ち物や生活環境、授業や食事など、日本の学校生活とは大きく違う部分があり、戸惑うこともありましたが、それ以上に「自分で工夫して適応する力」が身についたと感じています。
気候についても印象的でした。トゥーンバは気温だけ見るとそれほど寒くなさそうですが、実際は風が強く、体感温度はかなり低いことが多かったです。日本では夏から出発するため、到着直後は温度差に驚きました。オーストラリア人が半袖で過ごしている姿を見て「本当に同じ世界なのか」と感じるほどでした。寮生活は日本の学校では味わえない特別な経験でした。朝は点呼から始まり、食堂でみんなと食事をする生活リズムが定着していきます。夜も夕食後には勉強時間があり、9時半頃には各自が部屋で休むという規則正しい生活でした。最初は不自由に感じることもありましたが、次第にその規則性が心地よくなりました。
寮では週末になると生徒の多くが帰宅してしまい、残るのはほんの数人だけということもありました。しかし、その少人数で過ごす時間こそ、卓球やビリヤードを通じて学年を越えた交流が生まれるきっかけになりました。 異年齢の友人と打ち解けるのは簡単ではありませんが、遊びや会話を通じて自然に距離が縮まり、寮ならではの人間関係を築けたことは大きな財産です。
授業は週5日、一日5時間で行われ、哲学、数学、文学、日本語、化学、生物と幅広い科目を履修しました。中でも哲学の授業では「神の存在」についてディスカッションするなど、日本の高校ではなかなか触れられない内容に刺激を受けました。数学は比較的理解できましたが、生物や化学は難しく、授業についていくのは大変でした。
英語については、完璧に話せなくても問題はありませんでした。先生方もゆっくりと話してくれましたし、簡単な英語で聞き返せば大丈夫でした。実際に使ってみて感じたのは、「流暢さよりも勇気の方が大事だ」ということです。積極的に話しかけることで自然と理解も深まっていきました。
オーストラリアでの留学生活を通して最も大きかったのは「環境の違いを楽しみながら、自分で判断し、適応していく力」を養えたことです。持ち物一つとっても、日本なら当たり前にあるものが寮にはなかったり、逆に不要だったりしました。 そうした小さな発見を積み重ねるうちに、自分の中での柔軟さや対応力が少しずつ育っていったと感じます。
もちろん、気候や食事、授業内容の難しさなど簡単ではない場面も多くありました。しかし、それらを「不便」や「困難」と捉えるのではなく、「違いを知るチャンス」と受け止められるようになったのは、大きな成長だったと思います。これからの人生で新しい環境に直面したときも、オーストラリアでの経験を思い出して前向きに挑戦できる自信につながりました。(3年 陣野光一郎)
 )
)