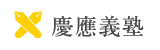フィールドワーク:民宿「みさき」の漁師さんに伺う。
フィールドワークとして実際の漁師の人にお話を伺うことができた。お話を伺ったのは北海道の尾岱沼(おだいとう)、別海町で漁師をしている富崎雅人さん。主にホタテと鮭を専門としていられ、漁師をやる傍ら民宿「みさき」の経営をしている方である。今回は漁に直接関わっている富崎さんの話から当事者だからこその物の見方、考えを教えてもらった。
Q.漁師になったきっかけはなんですか?
A.親の跡を継いだからです。しかし代々尾岱沼(おだいとう)に住んでいた漁師ではなく出稼ぎのような形で移ってきたらしいです。 (尾岱沼(おだいとう)では元々漁場がいいこともあり色々なところから漁師が来るそうです。)
Q.海とはどういう存在ですか?
A.そこで生活していることもあり従うべき存在です。
Q.自分の子供に跡を継いでほしいですか?
A.やりたければやってほしいが、特に強要はしていないです。
Q.漁師だからこその魅力やよさはなんですか?
A.頑張れば頑張るだけ結果がついてきます。その頑張った成果が直接現金につながります。
また富崎さんはクジラ漁や「the cove」にも意見をくださった。そもそも漁師とは海産物をとって生活する人たちのことで過度にとらないことは当たり前なのだそうだ。「the cove」については、これはイルカに限った話ではなくイルカ、クジラが食べる魚のことも考える必要がある。(特にクジラについては食事の際に食べる魚の量がかなり多いそうで、クジラに関しては近年増加しているらしく調査捕鯨という名目でしか獲れないことも考えると致し方ない、そうだ)イルカ漁、クジラ漁で生活している人たちもいることから批判すべきではないという。日本と欧米ではイルカを魚とみるか哺乳類とみるかで見方が異なっていてそうした見方の違いが肝になっている、とおっしゃっていた。
なお尾岱沼(おだいとう)について注釈をつけるともともとこの土地は人が多く漁師も不足しているわけでなく、たくさんいるという。家を継ぐのは一人だが雇われ漁師として生計を立てることもできるらしい。(漁師間では助け合うこともあるが基本は魚をめぐるライバル、という認識があるそうだ)前述の通り富崎さんはホタテと鮭を専門とされているが、別海町では鮭を獲る際イルカが紛れ込んでくることもあるらしくイルカ漁とあながち無関係ではないようだった。ちなみにお隣の標津町にはサーモンパークという鮭が川を上っていくところに施設を設置することで川上りの様子が見られる、という場所も存在する。
 )
)