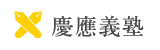フィールドワーク:東京都品川区 利田神社
フィールドワーク場所:東京都品川区1-7-17利田神社
(平成26年9月3日(水)実施)
1. 調査概要
利田神社に訪ね、江戸における鯨文化について探る。
2. 調査報告
 今回の調査における重要な点は利田神社にある鯨塚です。寛政10年(1798)に鯨塚という石碑が建てられました。この年、品川沖に迷い込んだ鯨を漁師たちが総出で捕らえるという事件があり、これが評判となって見物人が押し掛け、11代徳川家斉まで上覧になるという騒ぎになりました。この鯨のことをいわゆる「寛政の鯨」と呼びます。この鯨の残骨を集めて埋めた上に建てたのがこの鯨塚です。徳川実記によると、寛政の鯨は体長9間1尺(約16.5メートル)高さ6尺(約1.8メートル)と伝えられています。当時、普段捕鯨を行っていない地域で鯨をとらえた場合、村役人の見聞を受けたのち入札により払い下げることとされていました。品川も例外ではなく、寛政の鯨は41両3分余りで入札されました。この鯨は胴体部分が「こがね42枚」で売れ、残った頭の部分を「埋めて塚を築て葬りぬ。」とあります。つまり胴体部分だけが売られて、頭は地元の漁師により手厚く供養されたのです。
今回の調査における重要な点は利田神社にある鯨塚です。寛政10年(1798)に鯨塚という石碑が建てられました。この年、品川沖に迷い込んだ鯨を漁師たちが総出で捕らえるという事件があり、これが評判となって見物人が押し掛け、11代徳川家斉まで上覧になるという騒ぎになりました。この鯨のことをいわゆる「寛政の鯨」と呼びます。この鯨の残骨を集めて埋めた上に建てたのがこの鯨塚です。徳川実記によると、寛政の鯨は体長9間1尺(約16.5メートル)高さ6尺(約1.8メートル)と伝えられています。当時、普段捕鯨を行っていない地域で鯨をとらえた場合、村役人の見聞を受けたのち入札により払い下げることとされていました。品川も例外ではなく、寛政の鯨は41両3分余りで入札されました。この鯨は胴体部分が「こがね42枚」で売れ、残った頭の部分を「埋めて塚を築て葬りぬ。」とあります。つまり胴体部分だけが売られて、頭は地元の漁師により手厚く供養されたのです。
 他にも、この場所が江戸の昔に埋め立てられて利田新地と呼ばれていたことの解説板、鯨塚の大型看板、鯨の遊具やモニュメントを配した公園と、地域の人が熱心に歴史を残す努力をしていることが分かりました。また、鯨塚のすぐ横には屋形船の船着場があり、海のすぐそばであることが実感できました。
他にも、この場所が江戸の昔に埋め立てられて利田新地と呼ばれていたことの解説板、鯨塚の大型看板、鯨の遊具やモニュメントを配した公園と、地域の人が熱心に歴史を残す努力をしていることが分かりました。また、鯨塚のすぐ横には屋形船の船着場があり、海のすぐそばであることが実感できました。
参考文献
『品川の鯨碑と伝説』品川区教育委員会刊
 )
)